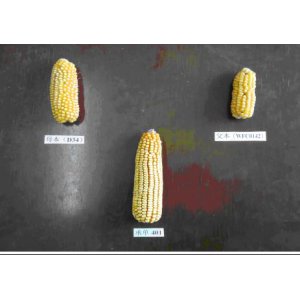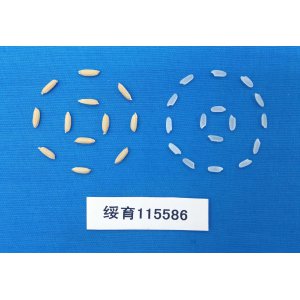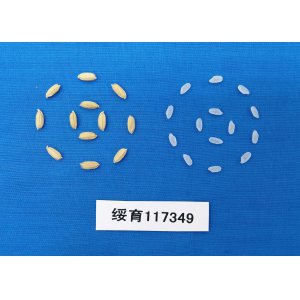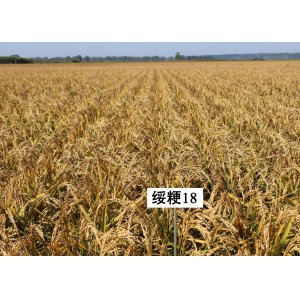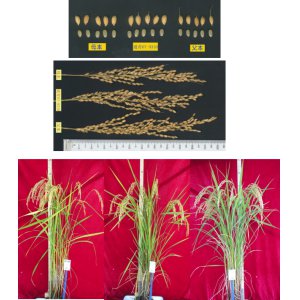クラリベイト・アナリティクスの事業部門である Web of Science Group は、本日、2019 年度の高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)リストを発表しました。このリストでは、特定出版年・特定分野における世界の全論文のうち引用された回数が上位 1%に入る論文を複数発表しており、後続の研究に大きな影響を与えている科学者や社会科学者が選出されます。高い影響力を持つ研究者の選出は、Web of Science Group の Institute for Scientific Information(ISI)に所属するビブリオメトリクスの専門家がデータやその分析結果に基づいて行っています。
2019 年度の主な選出結果は以下の通りです。
今年は、60 ヶ国近くからさまざまな分野で活躍する 6,217 名が高被引用論文著者に選ばれました。高被引用論文著者を最も多く輩出した国はアメリカで、今年選出された全著者の 44%を占める 2,737 名が選ばれました。世界で最も多くの高被引用論文著者を輩出した機関はハーバード大学で、203 名の研究者が選出されました。カリフォルニアからも優れた研究者が多数選出されており、スタンフォード大学から 103 名、またカリフォルニア大学バークレー校、サンディエゴ校、ロサンゼルス校からは、それぞれ 50 名以上の研究者が選出されています。
中国からの選出が急増しています。2018 年には 482 名であった高被引用論文著者が、2019 年は 636 名まで増加しました。Essential Science Indicator(ESI)の主要 21 分野で選出された研究者の数は、2014 年から 3 倍に増加しています。中国から選出される高被引用論文著者が増えたことにより、他の諸国からの選出が減少しました。イギリスの機関から選出された高被引用論文著者数は、2018 年の 546 名から、今年は 517 名となりました。ドイツとオランダからの選出も減少しています。
日本は2017年に72名が高被引用論文著者リストに選出されましたが、2014年より半分減少しました。2018年に91名まで増え、2019年に98名まで増え、第11位となりました。日本国内では、最も多く選ばれたのは東京大学でしたが、12名しか選出されませんでした。
日本は現在「第6期科学技術基本計画」を制定しており、新たな計画は2021年以降の5年間の科学イノベーション政策の基本を決める見込みです。11月6日に、日本科学技術振興機構(JST)の濱口道成理事長が、文部科学省科学技術及び学術政策研究所の主催する「フォーサイトシンポジウム~第6期科学技術基本計画に向けて日本の未来像を展望する」において、日本が厳しい現状に直面しているという意見を述べました。